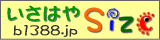床屋の親父が「農繁期が過ぎたらあっちもこっちも
痛い患者さん達で忙しくなるでしょう・・・」と
言われましたが、ハリ灸の一般的なイメージは
ハリをしたら痛みが楽になると思ってる方が
大半ではないかと思います。もちろん痛みが軽減されて
楽になるのは確かですが、私の行ってます「経絡治療」は
からだの気血のバランスを調整して自然治癒力を増しますので
痛みも和らぎ、続けているといつの間にか元気になってる
と言う方が大半です。そして気分も良くなりますので
治療の後はすっきりと身も心も軽くなります。
それはハリ灸を受けると「セロトニン」という
幸せホルモンが出るからなんです。
痛い患者さん達で忙しくなるでしょう・・・」と
言われましたが、ハリ灸の一般的なイメージは
ハリをしたら痛みが楽になると思ってる方が
大半ではないかと思います。もちろん痛みが軽減されて
楽になるのは確かですが、私の行ってます「経絡治療」は
からだの気血のバランスを調整して自然治癒力を増しますので
痛みも和らぎ、続けているといつの間にか元気になってる
と言う方が大半です。そして気分も良くなりますので
治療の後はすっきりと身も心も軽くなります。
それはハリ灸を受けると「セロトニン」という
幸せホルモンが出るからなんです。